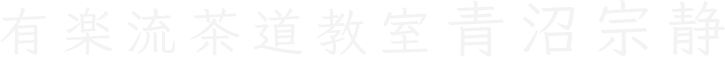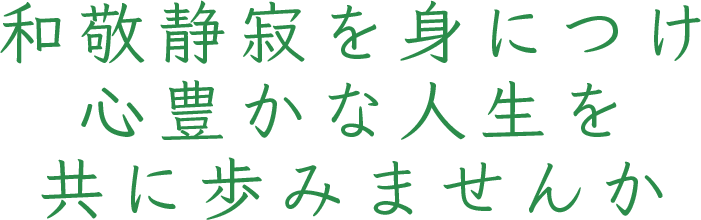
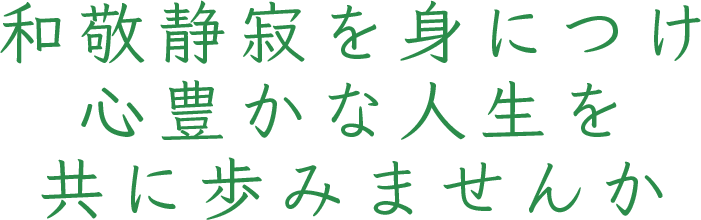
ごあいさつ
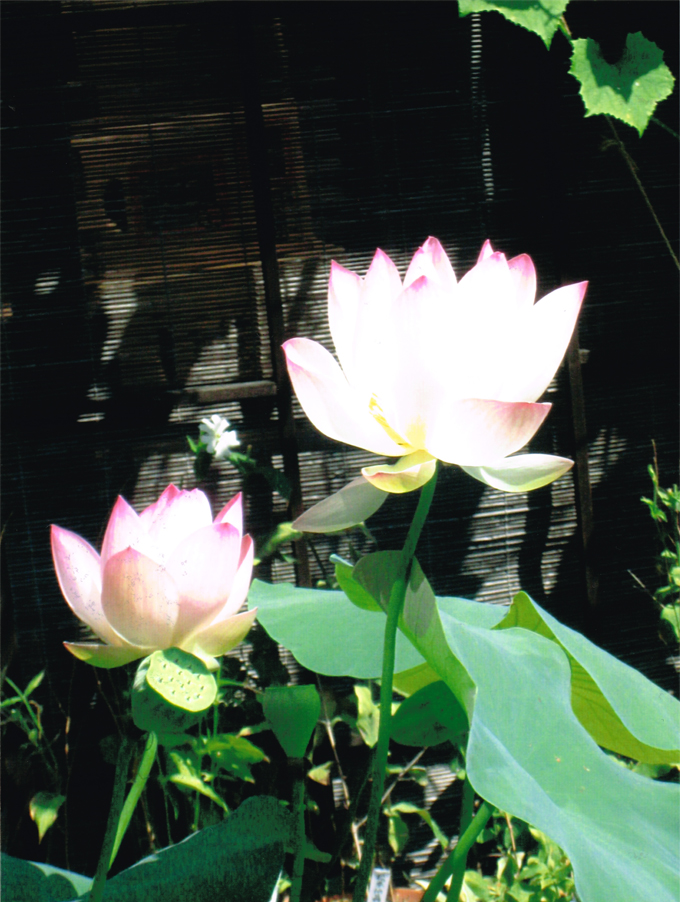
有楽流茶道教室 青沼宗静のホームページをご覧いただきありがとうございます。
日常生活から離れ、茶を点てる風雅なひととき。
身に付いた所作は自分自身であり、多くの経験を通して動じない心も養われます。
茶会では、様々なお役がありますが、一人一人が「心を込めて」
お客様に喜んでいただけることを目指しております。
この積み重ねが、自身の人生においても大切なことに
気付けることにつながると思います。
心豊かな人生を私達と共に歩みませんか。
有楽流茶道指南 青沼 宗静
有楽斎から始まる有楽流とは
・・・唯古人の跡をのみ認めて茶湯のすべてを知るならば、茶道の本意を失い、古人の意にそむくことになり、大きな誤りである。茶道の究極の境地は、その人々が時宜や時節に随って思いつくままに工夫を凝らした趣向を以て茶湯を行うことを本意とする・・・正伝集一巻より抜粋 (現代語訳は、本居宗元先生)
有楽流は、有楽斎(織田長益)が流祖です。信長の弟として生まれ、茶人として戦国の世を生き抜き、国宝茶室 如庵 を残しました。正伝集は台子手前・茶事の流れや道具の事・茶室など、有楽斎の茶の湯が記されております。
有楽斎の茶は、次男の頼長、四男の長政や五男の尚長、弟子の高島玄旦から孫の長好へ、さらに貞置(信長の孫)に受け継がれます。
貞置は千石の直参高家で、尾張藩二代藩主光友の頃、江戸屋敷に出入りして茶事を行い、猶子貞幹を尾張藩に送り、有楽流の根幹にしました。「武家茶道の系譜」より尾張藩の有楽流は、尾州有楽流に受け継がれ、貞置の茶は、その高弟松本見休により貞置が86歳の時に高覧を得て、後に貞要集五巻が著されました。
又、貞置の弟子に、土岐二三(土肥豊隆孫兵衛)がおり、私が知る限りでは80から86歳までの掛け軸や花入れ・茶杓・蓋置(二三花押有)が残り、掛け軸の内容から高い見識があったことが窺い知れます。昭和2年には没後200忌法要として関西方面の数寄者の二三会により、金戒光明寺に位牌が納められました。
有楽流は伝授を受けたものが次に伝えていく中で、作法や手前に違いがございます。
それはそれぞれの有楽流の歴史であり、時節やその場に応じた茶の湯を催すことが大切だと思います。
貞要集に「総じて茶湯は客を敬い、もてなす実を本意とす」と記されており、まさにその通りです。
不十分ではございますが、私の言葉で書かせていただきました。
稽古のご案内

是非一度、
稽古の見学にお越し下さい。
詳しくご説明いたします。
雰囲気や考えに共感出来、茶の湯を共に歩める方が増えることを願っております。
入門料と月謝・稽古に必要なもの
費用
| 入門料 | 10,000円 | (入門書発行) | |
| 月謝 | 月1回の稽古 | 3,000円 | (稽古は炭を使用) |
| 月2回の稽古 | 5,000円 | ||
稽古に必要なもの
使いふくさ・古ふくさ・扇子・懐紙・菓子切・ふくさ挟みか数寄屋袋
(使いふくさは洗心会のものを使用。他も購入される前にご相談下さい。)
稽古は、洋服でもかまいませんが、白いソックスをご持参下さい。